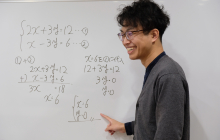ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞が決まったと聞いて、私がまず思ったのは、当のボブ・ディラン自身はこの受賞を素直に喜ぶのだろうか、ということでした。アメリカの、というか、世界のポピュラー音楽の歴史に特別な影響力を持った数々の歌で知られるその人は、これもまたよく知られているように、反戦と平和の生きた象徴であり、反権威と反権力の生きた象徴でもあり続けてきました。ノーベル賞はとびきりの権威です。その意義には古くから賛否両論がありますし、実際過去には、自らの信条から受賞を拒否した人もいました。案の定ボブ・ディランが受賞の知らせの後かなり長いこと沈黙しているとニュースで知って、やっぱりそうか、この人もノーベル賞は嫌なんだな、などと勝手に想像を巡らしました(その後本人から、受賞を喜んでいるというコメントが発せられたようで、このちょっとした騒動も収束したようです)。
こういった経緯はともかく、私が何よりも驚いたのは、従来ノーベル文学賞というのは言ってみれば、大文字の、大人の、高尚な文学に対して贈られるものという強いイメージがあったのに、そのノーベル賞が、大文字の文化からすれば長い間ずっと周縁のもの、一段どころか何段も低いものと見なされ続けてきたカウンターカルチャー※をある意味で代表してきた人に贈られることになった、という事実です(※「反体制文化」、つまり伝統文化や既成の文化を拒否する若者文化)。これには当のボブ・ディラン自身も、とても驚き、そしてうろたえたくらいではなかったかと思います。 ※『ジーニアス英和辞典 第5版』による。
ボブ・ディランという人は、今も、昔も、ロック、ポップの強力なアイコン(偶像視される人)です。もちろん天性の詩人、言葉の達人であり、それはたぶん古今のあらゆるポップアーティストの追随を許さないものでしょう。その彼に、自分は文学をやっているという意識はまったくなかったのではないかと思います。彼が書くのは歌であり、それもポップソングです。その歌には明らかなことですが、たいへん古い時代の黒人霊歌や黒人ブルース、また赤貧洗うがごとき漂泊のミュージシャンがギター1つで歌ったフォークソングの伝統が流れ込んでいます。それらの伝統は、主に社会の最下層の人々によって受け継がれていたものでした。ですから、今回の受賞を知って私が思ったのは、そういう歴史の闇に消えていった無数の無名の詩人たちの伝統にようやく日が当たったということ、アメリカ社会の最底辺で細々と、しかし力強く紡がれ続けていた伝統が、ようやく人類共通の財産として公式に認められるに至ったということでした。これは相当にエポックメイキングな事件ではないかと思います。西欧の上流社会の1つの大きな砦であるノーベル賞がそれを認めた意義は計り知れません。とはいえ、20世紀以来の歴史を通じて、商業的に成功を収めてきたのは、圧倒的にポップカルチャーのほうだったのではありますが。
私は、西欧の上流社会が生み出してきた大文字の文化(科学、芸術、思想等)にも惹かれますし、アメリカ社会の最底辺で紡がれていた伝統や、その伝統から大きな力を得てきたポップカルチャーにも惹かれます。昔からバッハやベートーヴェンが大好きだった一方で、ローリング・ストーンズやマイルス・デイビスも大好きでした。ただしかし、両者の間には大きな深い溝があり、それを埋めるのはほとんど不可能なことのように思えます。バッハを好んで聴いている時は、ローリング・ストーンズに熱を上げていた少し前のことは完全に忘れていますし、何かの拍子でまたローリング・ストーンズに夢中になる時が来れば、その時はもうバッハのことは無かったかのようです。飽きもせずせっせといろんなCDを買い続けてきた自分は、結局音楽産業にとっていいカモになっていただけじゃないかと虚しくなったりもします。が、しかし、実際にステレオから聞こえてくるものには、決してそんなことだけでは済ますことのできない何かが確かにあるようにも思えます。
バッハとローリング・ストーンズでは、その「何か」は同じものなのか、それとも根本的にまったく違ったものなのか、その辺りを上手く納得することができる言葉があればと思いますが、その言葉がどこにあるのかは、まったく見当もつきません。こういうことについては、たいへん多くのことがこれまで語られてきているのも事実ですが、それらはほぼ例外なく、どちらか一方の側からの一方的な議論にしかなっていないのは、まったくもって残念なことだと思います。
要はクラシック音楽のほうが優れているのか、それともポピュラー音楽のほうが優れているのか、という問題ではなく、両者はどちらも人間の魂の深い所に根ざしているはずなのだから、人間の魂の本源とでも言えるようなその場所を、クラシックとかポピュラーとかいったジャンル分けにはこだわらずに考え、言葉にしていく努力が必要ではないかと思います。
そもそも音楽のいろいろなジャンルというものが、音楽を売るための都合に合わせて人為的に作られたものであるように私には思えます。固定観念、というわけですが、こうした固定観念が当の音楽そのものの中身やその伝統にまでよくない影響を及ぼしてきたようにも思います。クラシック音楽は自分を高尚なものを解する上等な人間と見なす鼻持ちならない自惚れを助長するのにそれ自身まったく責任がなかったとは言えないし、ポピュラー音楽はポピュラー音楽で、理屈っぽくてお高くとまったクラシック音楽などクソ食らえと言わんばかりに虚勢を張るばっかりで、クラシック音楽の中に保存されてきたとても豊かで切実なものを見えなくしてしまうのに責任があったと言わざるを得ません。
ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞が本当にこういう固定観念を少しでも揺るがすものなのかどうかは(願わくばそういうものであってほしいと思います)、まだもう少し様子を見てからでなければ何とも言えません。
21世紀の世界は、相次ぐ戦争と大量破壊、大量殺戮の世紀とも言われた20世紀の世界から、どれくらい進歩しているのでしょうか。日々のニュースが伝えるのは、相も変わらず、いつ終わるとも知れない凄惨なテロリズムであり、そうでなくても、人が人にとって獣と化してしまったのではないかという不安と相互の不信が渦巻いているごく普通の社会の有り様です。
音楽は昔から、平和のイメージ、相争うものの宥和のイメージを描いてきました。ベートーヴェンの第九からはそういうイメージを他に例がないほど強く感じますし、エリック・クラプトンの美しいバラードからも、宥和のイメージは感じられます。しかし、どちらが描くイメージの中にも、世界全体が真に宥和している様が感じられるかと言えば、それは正直に言って難しいところです。クラシック音楽が描く宥和のイメージの中には、最良の作品においてさえ、社会の最底辺で生きる人々の声は響いていないように感じられますし、ポピュラー音楽のそれからは、人類の英知と言ってよいようなものに対する敏感さが欠けているように感じられます。およそこの世に存在するものすべての中で最も宥和に近いと思われる音楽でさえそうなのですから、他は推して知るべし、です。
さて今年も年の終わりが近づいてきました。私たちは誰もが皆、日々の当たり前の大変さに気をとられがちですが、時にはそういうことから離れて、普段なんとなく気になっていることを考えてみるというのは、意味のあることだと思います。ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞は、私に、自分が好きなものが孕んでいる(と思われる)問題に、改めて目を向けさせてくれるきっかけになりました。これからまた、巷では、年末に向けてあちこちでいろいろな音楽が賑やかに鳴ることでしょう。その究極は第九ということになるのでしょうが、今年はこれまでとはまた違った耳で、それらを聞くことになりそうです。
アルファ進学スクール水橋校 涌井 秀人