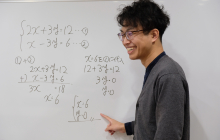だいぶ涼しくなりました。夏の記憶が急速に薄れていきます。季節は秋。いろいろなことに落ち着いて取り組めるとき。私にとっては、秋は何より読書の秋です。読みたい本が山積みです。普段は、1日の仕事を終えて眠りにつくまでの短いひととき、それから日曜日の昼下がりや夜の時間、自分の机に向かい読みかけの本を前に過ごします。
そうやって読みかけの本を前にして、独り半ば夢うつつに呑気に過ごすひとときが私にとっての至福のときです。読書が好きですが若かった頃から読むのが遅く、まったく多読ではありませんでした。1ヶ月に何冊読んだとか、よく一般の読書傾向の調査などで話題になりますが、そういう基準からすると私などはひょっとしたら、「読まない」ほうに入れられてしまうのかもしれません。
世間では多読とか速読とかがしきりに勧められています。1日に2、3冊読むとか1ヶ月に十数冊読むとかいう話を聞くと、私はすっかり恐れ入ってしまいます。自分にはとても真似できないし、世間には凄い人がいるものだと心底思いますが、仮にそういうのが普通だとすれば、私などは自分を何世紀も遅れて生まれてきた古代人のように感じてしまいます。
現代はインターネットで世界中がつながっている超高速情報時代。こういう時代には、読書という古い営みも(ただし古いと言っても、人類が「黙読」ということを始めたのは、歴史上割と最近のことなのだそうです。)、瞬時かつ大量の情報処理という社会が求める課題の影響を受けないわけにはいきません。今や書店へ行くと多読や速読を銘打ったハウツー本の数々が必ず目に飛び込んでくることは、そうしたことの何よりの証拠です。
こういう時代の動きに逆らって、ことさらに自分の「遅読」を正当化しようというつもりはありません。自分の場合はただ、ゆっくりと読むのが好きなだけで、ゆっくり読みながら、本の中の1つの言葉や1つの文が気になって、それについてあれこれ思いを巡らしてみたり、何十ページも前に戻ってある箇所をじっくり読み直してみたり、そうかと思えば今読んでいたのとは別の本のことが急に気になって一気にそこへ飛んでしばらくそっちのほうを読みふけったり、そしてまたそこから別の本へ飛ぶこともあれば、もともと読んでいた本に戻ってくることもあるというふうに、私は何かを読み始めると、思いが自然とあっちへ行ったりこっちに来たりというふうになるのに、特に何も考えず素直に従っているだけで、今こうして自分の読書のありようを書いていると、なんだか私の読書というのは、根無し草のようでもあり、落ち着きのない小さい子どもが無邪気に遊んでいるのに似ているなとも思います。
そう、私にとっての読書とは、まさに気ままで自由な遊びそのものです。他人に迷惑をかける遊びならいざ知らず、そうでない遊びについて人からとやかく言われるのはどうでしょう。本人が楽しんでやっていることを、遅いとか散漫だとか、役に立たない、得るところがないなどと言われても、はなはだ戸惑うだけです。いや実際は誰からもそういうことは言われませんが、しかし今の世に溢れる多読・速読を熱心に勧めるスローガンの類いを思うと、まるで自分は社会から責められているように、そればかりか無能の烙印を押されているようにさえ、感じてしまいます。
ところで以前ふとした折に手にした本の中に、こんな素敵な1節を見つけて、私は思わずほくそ笑んでしまったのでした。曰く、「偉大な文献学者フリードリヒ・ニーチェは、ものをきちんと読み取る能力の価値を説いてやまなかった。彼は『遅読』の教師を名乗り、これはスピードにとりつかれた時代の本性に刃向かうことだと考えていた。ニーチェにとって、精読は近代性に対する批判なのだ。言葉そのものの感触や形に注意を払うことは、言葉をただの道具として扱うのを拒むこと、ひいては、言語が商業と官僚主義のせいで、薄っぺらな紙のように磨り減った時代を拒むことだ。ニーチェの『超人』は、Eメールを使わない。」(テリー・イーグルトン『詩をどう読むか』川本皓嗣訳、岩波書店)
私はEメールを使うので、ニーチェの「超人」とは縁もゆかりもありませんが、ただ、ここで言われていることにはとても共感を覚えます(自分のが果たしてニーチェの言う「精読」かどうかは分かりませんが)。言葉というものには、それ自体の運命があるように思います。言葉は万人のものである以上、完全に著者の意のままになるものではありませんし、同じく読者の意のままになるものでもありません。同じ1つの言葉が、時代や場所が変わると違う意味を持つようになるということもあります。ある言葉に触れるとは、その言葉の向こうにある長大な時の流れや果てのない広大な世界に触れることです。1冊の本の中、いやその1ページの中にさえ、人類の悠久の記憶に通じる入り口が口を開けて、深くていねいに読む者を待っていると言ってよいと思います。瞬時に大量の情報の要点をつかみ取ることも大切かもしれませんが(現代はそういうことを絶えず人間に求めてきます。大人にも子どもにも。)、そういう読み方からこぼれ落ちてしまうものもたくさんあるということは、誰もが考えてみるに値することだと思います。ちなみに上で紹介した1節の書き手によれば、「文献学者」とは「言語を愛する者」。そして言語とは、1人1人の人間と文明の全体を結ぶ「架け橋そのもの」となります。
さて、今日も私は、いつも読みかけのままの気に入りの本を広げて、誰にも邪魔されず、気ままで自由な遊びを楽しみたいと思います。私は、今さらどう頑張ったところで、ニーチェのような徹底的な読み手にはなれないでしょう(少しでも近づきたいとは思いますが)。でもいいのです。たとえ毎日わずかの時間であっても机に向かい読みかけの本を広げるひとときに勝る悦びはありません。そこでは日々の苦労が、悩みが、社会とか文明とか自然とか、はたまた宇宙といった大きな連関の中に自然に移し入れられ、普段いろいろなことに追われあたふたしているときにはおよそ思いもよらない鮮やかな景色が目の前に広がることがあります。
こういうことは、読書を何か実務的なことに役立たせるとか、あるいは何か、実益を超えた、人類や社会にとって本質的に有益なものを提示するとかいったこととは何の関係もない、純粋に個人的な遊びでしかありません。その意味ではこれはまったくの無力な行為です。しかし遊びを侮ることなかれ、です。人間社会にとって本当に有益なものは遊びの中から生まれてくる、と言い切ることはできませんが、そうではないと言い切ることもできないのです。社会のお仕着せを脱ぎ去ったところでなされる遊びの中には、社会をいずれ根本的に変えていく力が眠っているのではないかと、私はかなり真剣に思っています。それは、子どもが自発的に行う遊びについても、言えると思います。
ともかく私たちは、何かの役に立つということに今や過度にこだわりすぎているのではないでしょうか。一見意味がないように思えることが、本当に意味がないなどと誰が言えましょう。そんなふうに決めつける人は、とんでもない思い上がりです。私たちはもう少し気持ちを楽にして、もう少し遊ぶことを大切にしてもよいのではないかと思います。大人も子どもも。
アルファ進学スクール水橋校 涌井秀人