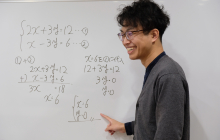この頃はモーツァルトの音楽を気に入ってよく聴いています。教室ではいつもごく小さな音量で音楽をかけているのですが、それもこの頃は、モーツァルトばかりです。
モーツァルトと言えば、何かと忙しい現代人の疲れた心を癒やすとか、潜在意識に作用して、人の中に眠っている能力を目覚めさせるのに効果があるとか、あるいは胎教だとか、とにかくいいといったことがひと頃しきりに言われましたが、最近はどうなのでしょう。私はそういうようなことはあまり気にせず、1人の単なる音楽好きとして、その時その時の興味に従って聴いているだけです。教室に来てくれている子どもたちは、教室で音楽が流れていても、それが何なのか、意に介することはまったくと言っていいほどないでしょう。それでいいと思っています。単なる私のわがままです。
言うまでもなく大作曲家で、ピアノ独奏曲から弦楽四重奏曲などの室内楽曲、とてもたくさんのピアノ協奏曲、交響曲、それに個性的な宗教曲、そしてもちろんオペラまで、モーツァルトが生きて活動していた当時(今から200年以上も前)あったさまざまな音楽ジャンルで、モーツァルトが手をつけなかったジャンルはないと言われるくらい、そして少なからぬ傑作を遺さなかったジャンルはないと言われるくらい、とてもたくさんの評価の高い作品を作曲しました。しかもたった36歳でこの世を去ったのですから、すっかり嫌に(?)なってしまいます。モーツァルトと自分を比べるなど笑止千万ですが、モーツァルトよりもはるかに長く生きてきたけれど、ここまでいったい自分はどんな価値あるものを作ってきたのかと、嘆きの1つも出ようかというものです。こういうことは、モーツァルトに対してに限らず、割とよく思います。人間の歴史において、偉大なことを成し遂げた人々。そうした人々と張り合おうとする(?)気持ちがずっと自分にはあって、しかもそうした気持ちを持てあましています。時は容赦なく過ぎる。時は金なり。さりとて相変わらずの自分‥。つい嘆かわしくなりますが、他の人はどうなのでしょうか。
ところで、モーツァルトの音楽を聴いていて、気になることがあります。一般にその音楽は、気品があって美しいものとされています。もちろん古くは批評家の小林秀雄さんなどが言ったように、悲劇的で深刻な内容を持つ音楽という見方も強くあるのは確かですが、冒頭に述べたような評価につながる明るい肩の凝らない音楽と見なされることは、今も多いと思います。ベートーヴェンにあるような暗さ、深刻さがモーツァルトにはないだとか、悪く言えば軽い音楽で内容が乏しいといった見方は今も珍しくありません。でも、ピアノ曲でも交響曲でも、とにかく何でもいいから適当にCDをかけて聴いていると、その音楽の中から、まったく意外と言っていいような、誤解されるのを恐れずに言えば、何か「狂暴さ」のようなものが聞こえてくることがあります。というか、いったんそういうものが気になり始めると、もう、モーツァルトのどんな作品を聴いても、それが聞こえてくるような気がして、美しい音楽に心を洗われるような心地になりつつも、それと同時に、いったいこれは何だと思ってしまいます。それは深刻でかつ激しい音楽の代名詞のように言われるベートーヴェンの音楽からでさえ、あまり聞こえてこないものです。
とはいえちょっと種明かしをすれば、私がそんなふうに思ったのも、こちらもまた日本を代表する音楽批評家の吉田秀和さんが書いた文章の中で、そういうことに触れた部分に何度か出くわしたからでした。その中から1つの箇所を引くと、「哀悼と歓喜が、稲妻のように交錯する。率直だが細心。厳粛さの中に、確然と思いきって、つきまぜられた狂暴さ。単純さの中にある、荒々しい苦々しさ。さらにその底には、何をしても、どこに向かってかけ出しても、不思議な強さと明るさとをもって自分について廻る確信―いや、自分でも対象と内容のはっきりしない、こういう信念を何と呼んだら、いいのだろうか?―、そういうものをもてあましているような、もてあましながら、それと戯れているようなもの」(吉田秀和『モーツァルト』講談社学術文庫から)。
「単純さの中にある、荒々しい苦々しさ」。「さらにその底には、...不思議な強さと明るさとをもって自分について廻る確信」。「そういうものをもてあましているような、もてあましながら、それと戯れているようなもの」。これは、成長しつつある子どもに見られるものとも共通しているように思えます。子どもは決して可愛いだけのものではありません。子どもは明らかに、「狂暴さ」を内に含んでいます。それを見て大人は戸惑いますが、それは大人がかつて自分自身子どもだったときには持っていたものでした。たぶん例外なく。そしてそれは、目の前の生活や仕事にかまけて普段忘れているだけで、今でもなお、大人のうちにもあるものだと思います。
人間が生きていくのは一筋縄ではいかないことです。人生は単純で美しければ、それに越したことはないのだろうと思いますが、実際はまったくそうはいきません。人生の途上には、数限りない躓きの元が転がっていて、思わぬしくじりと失望の連続こそが本物の人生だと思いたくなるほどです。そういうものである人生を、それでも明るく力強く進んでいくためには、ある種の狂暴さが、必要かもしれません。失望からの跳躍。人生という得体の知れない巨大なものを、無理矢理にでも組み伏せようとする乱暴な強さ。
モーツァルトが生きて活動した時代は、哲学者ならカントが、文学者ならゲーテが、それぞれの生涯の大事業に取り組んでいた時代でもあります。18世紀は啓蒙主義の世紀でした。社会の近代化の進展とも相まって、それまでの常識や伝統や権威が音を立てて急速に崩れていった時代でした。当時の人々は、自分以外頼れるものは何もない荒野にいきなり投げ出されたも同じでした。当時の大作曲家や哲学者や文学者はそれぞれに、突然行く手に立ち塞がった、人生という得体の知れない難物との格闘の仕方を追求していたのだと思います。真摯に、強い意志を持って。
翻って現代を考えてみると、モーツァルトたちが生きた時代とはまったく比べものにならないくらい、世界ははるかに複雑なものとなり、現代を生きる人間の人生の得体の知れなさは、そのため、もはや底なしとも言えるものになっています。こういう時代に自分自身の確かな人生を生きていくのは、至難の業です。どうすればそういうことができるのか。それには、組み伏せようのないものを無理矢理にでも組み伏せようとする乱暴な強さ、それは覇気と言っても独立心と言ってもよいものだろうと思いますが、そういう強さを持つだけでは不十分ではないかと思います。弱さと言っては語弊があるかもしれませんが、あるがままのものに謙虚に向き合う姿勢も必要だろうと思います。
ところで、モーツァルトの音楽から聞こえてくる一種の強引さ―それは胸のすく強引さです―は、18世紀末にフランス革命を引き起こしたものと相通じるように思います。その音楽には、自由・平等・友愛をモットーに、自分自身の確かな人生を生きようとして突き進んだ当時の市民たちの気概が込められているようです。そこから私たちが学べることはとても多いと思います。先人たちの経験。歴史は、ただ歴史の教科書の中だけにあるのではありませんし、ただの暗記物でしかないなどということは、絶対にあり得ません。モーツァルトの音楽のような、最も世俗的なことから遠いと思われがちなものの中に、歴史は折りたたまれて入っているという目線を持つなら、いろいろなものが全然違ったふうに見えてきます。そういう目を持つことが、私にとっての究極の学びです。
アルファ進学スクール水橋校 涌井 秀人