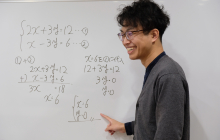先日、塾の広告チラシを配って歩いていたとき、その日はよく晴れた、5月にしてはかなり暑い日でしたが、ちょうど海岸沿いの道にさしかかり、高いコンクリートの防波堤が目に入りました。不意に海が見たくなって防波堤の上に上がると、そこには富山湾の素晴らしい景色が広がっていました。富山の海など普段見慣れているはずですが、その日防波堤の上から見た海は、自分には格別なものに感じられました。いつも見ている富山の海はどういうわけか泥水のような色をして濁っているイメージが強いのですが、その日見た海は、空の青を映して、少し凪ぎ気味の海面が、はるか遠くのほうまで青く眩しく光っていました。1年のうちでもあんなに海がきれいに見えるのは、そういくらもあることではないだろうと思います。海を見ていたのはほんの短い間にすぎませんでしたが、ずいぶんと心の深呼吸ができたように感じ、思いがけない贈り物のように思いました。
そのときふとフランスのある詩人のことを思ったのでした。ポール・ヴァレリー。19世紀後半から20世紀前半にかけて生きた人。宮崎駿さんの映画『風立ちぬ』をご覧になられた方であれば、映画の冒頭で紹介されていた詩の一節「風立ちぬ、いざ生きめやも (風が立つ、生きようと試みなければならない)」を覚えておられるかもしれません。この一節はポール・ヴァレリーのものです (「海辺の墓地」という詩の一節。この訳は小説家の堀辰雄のもの)。私にとっては、ヴァレリーは海についての詩を書いた詩人という印象の強い人です。昔学生だったときに親しんだのが鈴木信太郎訳の岩波文庫版で、旧字・旧仮名遣いの独特の格調高い訳だったためもあってか、非常に難解・晦渋なもので、まだ若かった私には、正直ほとんどただのひと言も何を言っているのか分からなかったことを覚えています。
学生生活の中で、勉強を含めいろいろなことに悩んでは、天気のよい日など、そのヴァレリーの詩集を持って自転車に乗り、1人海に出かけたものです。大学の授業をサボって出かけたこともありました。鬱屈した思いを抱えて、平日の日中ですからあまり人気のない海岸を意味もなく歩いてみたり、適当な場所に腰を下ろして気ままに詩集を広げ、難解で何を言っているのかは皆目分からなかったけれどもなぜか強く惹きつけられる言葉を眺めてみたり、かと思えばすぐに読むのにも飽きて砂浜の草の上に寝そべり、目をつぶって寄せては返す波の音をじっと聞いていたりして、日が傾いて太陽が水平線の下に沈もうかという時間まで1人で過ごしました。そういうことは若かった頃の私にとっては、何よりの精神安定剤の役目を果たしてくれていたのだと思います。青春時代の美しくもほろ苦い記憶です。
ポール・ヴァレリーの詩集は私にとっては崇高なものであり、しかも青年時代の夢や希望と現実に味わう数々の失望感と無力感の間のギャップを、自分の想像力の中で一挙に埋めてくれる、そんな魔法の道具だったのかもしれません。若かった頃の私は、西欧の優れた文物への憧れの思いばかり強くて、現実に日々こつこつと地味で面倒くさい努力を重ねて憧れの対象に少しでも近づこうとする意志の力を欠いていました。私にとっての詩とは、この矛盾した苦しい状態からひょっとしたら一気に抜け出すことができるのではないかと思わせてくれる、またとないものだったのかもしれません。意味が分からないということは、そこでは無意味なことでないばかりか、どうしても必要なことだったのではないかとも思います。「海邊 (うみべ)」とか「午 (まひる)」、「松の樹間 (このま)」といった言葉、いや言葉というよりも、最近ではほとんど見かけなくなった活版印刷の味わいのある文字に反応して、そこからぼんやりと気ままに自由に、遠い架空の異国の海のイメージが自分の頭の中に広がっていくのに身を委ねるひとときは、目覚めたまま美しい夢を見ているようでもあり、まさしく逸楽でした。その白昼、夢を見ている間は、現実のふがいない自分をあらかた忘れていられるのです。今思えば、そのときは夢を見る以外何の役にも立たないことをしていたわけですが、詩を楽しむとか味わうといったことの本質的部分を自分は知らず知らずのうちに経験していたのかもしれない、とも思います。ろくに勉強もせずそんなことばかりしていた私をいつも温かく見守ってくれた私の恩師、そして私の家族には感謝する他ありません。
思えば私が学生時代を過ごした頃は、スマホはおろかパソコンもまだまだ普及しておらず、若い人が何をするでもなくぼんやり時間を過ごすことは、特に当時も今も変わり者なのかもしれない私でなくとも、割とまだ世間一般に当たり前にあったように思います。私ぐらいの世代までの人間にとっては、学生時代とは大人の社会に出る前のモラトリアム期間として、むしろ暇を積極的に謳歌するべきものだったのではないかと思うのですが。それがいつ頃からか若い人が誰も彼もあくせくするようになり、将来につながる勉強に学生時代熱心に取り組むことが当たり前になり、勉強していない時間はアルバイトに精を出すことが当たり前の生き方に変わってきて、今ではそういうことに加えてSNSで友だちその他の人と始終やり取りし合うようにもなっており、いったい今の若い人たちにはぼうっと過ごす時間なんてあるのだろうかと、私は不思議でなりません。
思えば昔はニートとか引きこもりという言葉はありませんでした。それはそういう人がいなかったからではなく、今の時代よりもそういう人が白い目で見られることが少なかったためではないかと私は思っています。そもそも人が、成長していく過程のどこかで時間を気にせずぼんやり過ごしたり引きこもったりすることは、実は無意味なことでは全然なくて、たくさんのいろいろな物や情報に溢れた人間社会の中で、その人その人にとって有意義なものは何で、自分はどういう人生を歩いていきたいのかを見極めるための時間というのは、端から見るといかにも非生産的な無駄な時間としか思えないような、そういうものとしてしかあり得ない時間なのではないかという思いを、私はずっと強く持っています。「退屈とは、経験という卵をかえす夢の鳥だ」と批評家のベンヤミンは言います※。こういう発想を見直してみる意義は、大いにあるのではないでしょうか。
※ヴァルター・ベンヤミン「物語作者」から。『ベンヤミン・コレクション2 エッセイの思想』浅井健二郎 編訳、ちくま学芸文庫。
ところでポール・ヴァレリーのこと、個人的なことに返りますが、その難解な詩に対する自分の関わり方は、教養というものに対する自分の関わり方全般を象徴しているように思います。それは一方では強い憧れであり、価値の高い対象を理解したい、また味わいたいという欲求、少なくともそこにできるだけ近づきたいという欲求です (教養主義あるいはその名残と言えるでしょう)。しかしもう一方には、その強い憧れの対象にどうしても近づくことができない、それを自分のものにすることができないというもどかしさ、挫折感があります。これは実用的な知識との関わり方ではなく、あくまでも古い意味での教養との関わり方なのですが、自分の場合は少年時代に始まって未だに解決できていません。言わば生涯の課題になっています。学生時代にはそれこそ全身全霊で格闘しましたが、満足のいく結果は得られていません。今の若い人々の古い教養との関わり方はどうなっているのか、興味があるところです。自分の場合はおそらく世代的なこともあるのでしょう、とても屈折したものですが、今の若い人にとっては、すでに教養などというものには特別な価値はないのかも知れません。今の若い人の多くにとっては、学校をサボってまで読む価値のある本があるなどというのは、信じがたいことかもしれません。そんなふうであって果たしてよいのだろうかと、私は思うのです。
アルファ進学スクール水橋校 涌井 秀人